ストレージ・ネットワークはどこへ向かうのか:上司のためのストレージ・ネットワーキング (6)(1/2 ページ)
ストレージ・ネットワークの役割が拡大を続けるなか、そのインテリジェント化を目指した技術やコンセプトが次々に登場しつつある。連載の最終回として、ストレージ・ネットワークの最新動向を紹介する
前回は「ストレージ・ネットワークの拡張」と題して、より大規模なSAN環境に移行する背景と移行の際の手法、そしてそれぞれの手法におけるメリットおよびデメリットなどを解説した。最終回となる今回は、現在ストレージ・ネットワークの分野で登場しつつあるさまざまな技術を紹介していきたい。。
ストレージ・ネットワークにかかわる最新技術の可能性と注意点
最終回のタイトルを仰々しくも「ストレージ・ネットワークはどこへ向かうのか」としたが、データアクセスのインフラとしてのストレージ・ネットワークに求められる役割は、今後ますます大きくなっていくと考えられる。サーバとストレージ、さらにはクライアントがつながるストレージ・ネットワークは、「サーバ管理の効率化」「ストレージ管理の効率化」「クライアントアクセスの効率化」といった機能を包含し、より「インテリジェント」なものになっていくだろう(図1)。本稿では、「ストレージ仮想化」「サーバ仮想化」「ファイルアクセス技術」「ILMとFLM」という4つの技術に関して、それぞれのメリットと検討および導入における注意点を解説する。
ストレージ仮想化
ストレージ仮想化は以前より注目されていた技術で、すでに多くのベンダから製品が提供されている。ストレージを仮想化することで、ユーザーは物理的なストレージを意識することなく、柔軟に複数のストレージを管理できる。例えば、複数の物理ストレージから構成される「仮想ボリューム」を作成して自由に容量を追加したり、サーバに意識させずにストレージ装置間でデータ移動を実施することなどができる(図2)。
ストレージ仮想化を実現するには、いくつかの形態がある(図3)。1つは専用のアプライアンス装置やソフトウェアを利用するものだ。以前から提供されていた形態で、現在最も普及しているといえる実装方法だろう。この場合すべてのI/Oがアプライアンス装置もしくはソフトウェアを通過するため、パフォーマンス上のボトルネックになる懸念がある。特にソフトウェア製品として提供されているものについては、動作環境のハードウェアを十分に注意して選定することが望まれる。
2つ目は「ストレージを仮想化するストレージ」を用いる方式である。仮想化ストレージの配下に複数の物理ストレージを移し、仮想化ストレージ以外のストレージをサーバから隠ぺいする形態だ。ハードウェアベースであるため十分なパフォーマンスを発揮できるが、実現できる機能やサポートされる物理ストレージは仮想化ストレージに依存する。また、そもそもストレージ仮想化のメリットの1つは特定の物理ストレージベンダ依存から脱却することだが、ストレージベースでの仮想化ではやはり仮想化ストレージを提供するベンダに依存することになる。
近年注目を集めているのが、「インテリジェントスイッチ」を導入してストレージを仮想化する方式である。ストレージ仮想化に対応したSANスイッチを専用の端末から制御する。これらの間のインターフェイスは、ANSI T11.5委員会で「FAIS (Fabric Application Interface Specification)」として標準化されている。この形態ではデータI/Oと制御用のI/Oが分離して処理されるため、高負荷時にもパフォーマンスのボトルネックが発生しにくい。しかし現時点ではまだ市場での実績が多いとはいえず、導入に際しての十分な事前検証が欠かせない。
上記のいずれの方式で仮想化を実現するにしても、障害時の切り分けはこれまでよりも困難になる。例えばインテリジェントスイッチで仮想化を行っている場合には、「障害が発生しているのがストレージ側なのかスイッチ側なのか」「ハードウェア障害なのかソフトウェア障害なのか」など、単純にサーバを物理ストレージに接続する場合に比べて考慮しなければならない点が増える。従って運用上のメリットばかりに注目するのではなく、導入する製品の物理的あるいは論理的な仕組みについてもきちんと理解しておかなければならない。
サーバ仮想化
ストレージ・ネットワークにはストレージだけではなく、「サーバ」も接続されている。ストレージ・ネットワークの規模が大きくなるにつれて接続されるサーバ台数も増加するため、「増え続けるサーバ」への対処も管理者にとっては頭の痛い問題だ。
サーバ仮想化について理解するには、まず「サーバ」の定義をあらためて見直す必要がある。一般に物理的なサーバには、「CPU」「メモリ」「NIC(Network Interface Card)」「ディスクドライブ」「OS」「アプリケーション」などのコンポーネントが含まれている。1台の物理サーバには、上記のコンポーネントが1つもしくはそれ以上存在するのが一般的だ。つまり、これまでの物理サーバ環境では、「サーバ(物理サーバ)」と「コンポーネント」の関係は1:1もしくは1:nであった。しかし「仮想化された」サーバ環境では、この関係がn:1になり得る。例えば、複数の(仮想)サーバで1つの物理CPUやNICを共有するといった使い方が可能になる(図4)。
仮想サーバ環境では、「サーバ」は物理的なコンポーネントから独立したものとして認識される。つまりCPUやメモリ、HDDといった物理リソースをその用途や求められるパフォーマンス、可用性などに応じて柔軟に組み合わせて、仮想サーバを動的に構成することが可能となる。従って、仮想サーバ環境を構築する場合には、それぞれの物理コンポーネントは「切り離されている」方が実装しやすい。例えばストレージ・ネットワークを中心にしてディスクドライブには外部ストレージを利用し、OSやアプリケーションは外部ストレージ上にインストールしておけば、コンピューティングリソースとしてのCPUおよびメモリと組み合わせて自由に仮想サーバをインスタンス化することができる(図5)。
システム拡張やハードウェア障害などにより物理サーバを交換するような場合には、サーバを動的に構成できるメリットは運用保守の観点からは非常に大きい。従って、前回紹介したブレードサーバを用いたシステムなどでは、サーバの仮想化技術は検討に値する選択肢になるだろう。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
人気記事ランキング
- 爆売れだった「ノートPC」が早くも旧世代の現実
- HOYAに1000万ドル要求か サイバー犯罪グループの関与を仏メディアが報道
- GoogleやMetaは“やる気なし”? サポート詐欺から自力で身を守る方法
- Appleの生成AI「MM1」は何ができるの? 他のLLMを凌駕する性能とは
- キヤノンがグローバル330社の経営管理基盤を構築 連結決算を合理化した方法は?
- PAN-OSにCVSS v4.0「10.0」の脆弱性 特定の条件で悪用が可能に
- SharePointのダウンロードイベントログを回避する2つの手法が見つかる
- OpenAI Japan設立 岸田首相への宣言から1年 日本語特化GPT提供へ 速度3倍コスト半減
- OTセキュリティ関連法改正で何が変わる? 改正のポイントと企業が今やるべきこと
- Rustの標準ライブラリにCVSS 10.0の脆弱性 任意のシェルコマンドを実行されるリスク
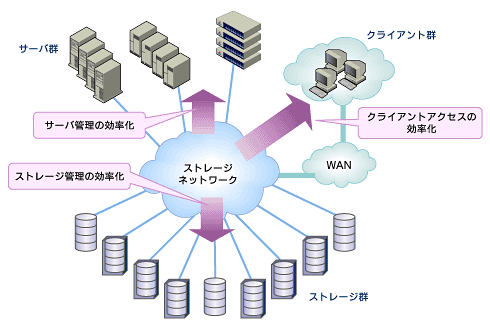 図1 ストレージ・ネットワークの進化
図1 ストレージ・ネットワークの進化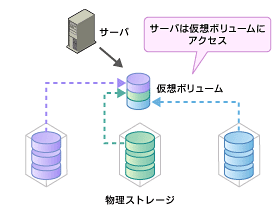 図2 ストレージの仮想化
図2 ストレージの仮想化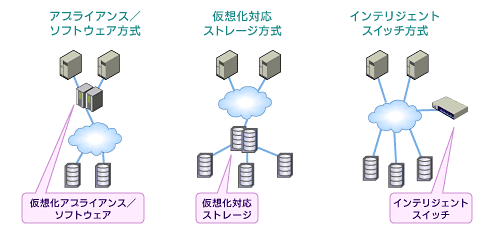 図3 ストレージ仮想化を実現する各種の形態
図3 ストレージ仮想化を実現する各種の形態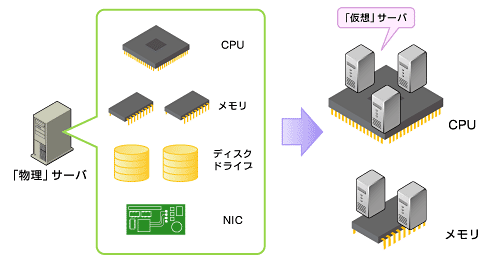 図4 サーバの仮想化
図4 サーバの仮想化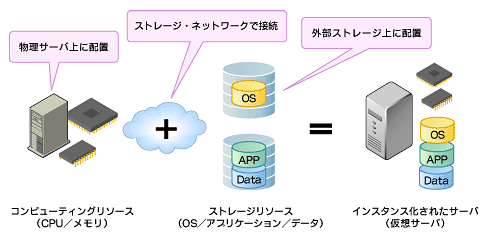 図5 リソースを柔軟に組み合わせて論理的なサーバを構築
図5 リソースを柔軟に組み合わせて論理的なサーバを構築


