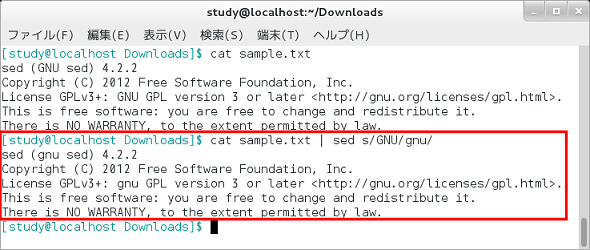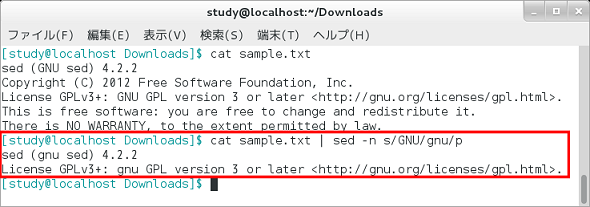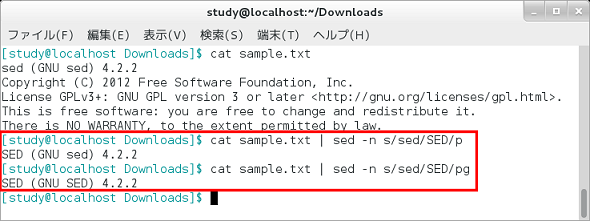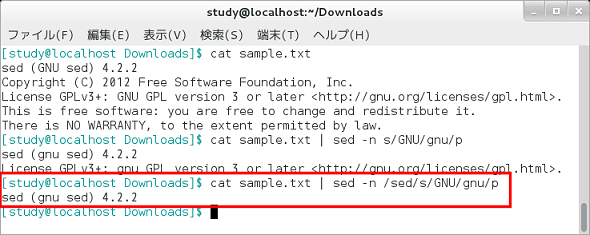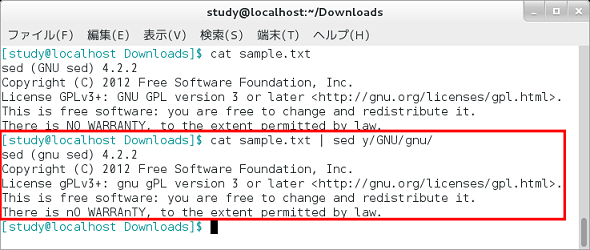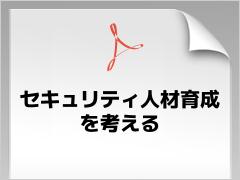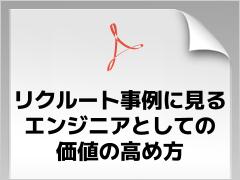【 sed 】コマンド(基礎編その4)――文字列を置き換える/置換した行を出力する:Linux基本コマンドTips(56)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。前回、前々回に続き、今回も「sed」コマンドの基礎編を解説します。
この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。
本連載では、Linuxの基本的なコマンドについて、基本的な書式からオプション、具体的な実行例までを分かりやすく紹介していきます。前回、前々回に続き、今回も「sed」コマンドの基本的な使い方を解説します。
sedコマンドとは?
「sed」は「Stream EDitor」の略で、「sed スクリプトコマンド ファイル名」で、指定したファイルをコマンドに従って処理し、標準出力へ出力します。ファイル名を省略した場合は、標準入力からのデータを処理します。sedコマンドでは、パイプとリダイレクトを活用するのが一般的です。
sedコマンドの主なオプション
sedコマンドの主なオプションは次の通りです。
| 短いオプション | 長いオプション | 意味 |
|---|---|---|
| -r | --regexp-extended | スクリプトで拡張正規表現を使用する |
| -e スクリプト | --expression=スクリプト | スクリプト(コマンド)を追加する |
| -f スクリプトファイル | --file=スクリプトファイル | 実行するコマンドとしてスクリプトファイルの内容を追加する |
| -i | --in-place | ファイルを直接編集する |
| -i拡張子 | --in-place=拡張子 | ファイルを直接編集し、指定した拡張子でバックアップする(※「-i」と「拡張子」の間には空白を入れない) |
| --follow-symlinks | -iで処理する際にシンボリックリンクをたどる | |
| -n | --quiet,--silent | 出力コマンド以外の出力を行わない(デフォルトでは処理しなかった行はそのまま出力される) |
| -l 文字数 | --line-length=文字数 | lコマンドの出力行を折り返す長さを指定する(※「-l」と「文字数」の間には空白を入れる) |
| -s | --separate | 複数の入力ファイルを一続きのストリームとして扱わずに個別のファイルとして扱う |
| -u | --unbuffered | 入力ファイルからデータをごく少量ずつ取り込み、頻繁に出力バッファーをはき出す |
| -z | --null-data | NUL文字で行を分割する(通常は改行で分割) |
| --posix | 全てのGNU拡張を無効にする | |
sedのスクリプトコマンド
sedでは、「アドレス」と「コマンド」の組み合わせで処理を指定します。
アドレスには行番号や正規表現による指定が可能で、省略した場合は全ての行が処理の対象となります。
| コマンド | 意味 |
|---|---|
| = | 現在の行番号を出力する |
| a テキスト | テキストの追加。指定した位置の後ろに[テキスト]を挿入する(挿入するテキストに改行を含める場合は、改行の前にバックスラッシュを置く) |
| i テキスト | テキストの挿入。指定した位置の後ろに[テキスト]を挿入する(挿入するテキストに改行を含める場合は、改行の前にバックスラッシュを置く) |
| c テキスト | 選択した行を[テキスト]で置換する(挿入するテキストに改行を含める場合は、改行の前にバックスラッシュを置く) |
| q | これ以上入力を処理せずに終了する(未出力分があれば、出力してから終了する) |
| Q | これ以上入力も出力もせずに終了する |
| d | 指定した行を削除する |
| p | 処理した内容を出力する(「-n」オプション指定時は「p」コマンドがないと何も出力されなくなる) |
| s/置換前/置換後/ | [置換前]で指定した文字列にマッチした部分を[置換後]に置き換える。複数マッチした場合は先頭のみ置換、全てを置換したい場合は、「s/置換前/置換後/g」のように「g」オプションを指定する |
| y/元の文字列/対象文字列/ | [元の文字列]にあるものを、対象文字列の同じ位置にある文字に置換する(「tr」コマンドのように使用できる) |
| # | コメント(スクリプト中、「#」以降がコメントとなる) |
文字列を置き換える
文字列の置き換えは「s」コマンドを使って、「s/置換前/置換後/」と指定します。例えば、文字列「GNU」を「gnu」に置き換えるならば、「s/GNU/gnu/」と指定します。
置き換えのパターンには、正規表現や部分文字列の指定も可能です(次回解説)。
コマンド実行例
sed s/GNU/gnu/ ファイル名
(「GNU」を「gnu」に置き換える)
cat ファイル名 | sed s/GNU/gnu/
(「GNU」を「gnu」に置き換える)(画面1)
置換した行だけを出力する
文字を置換した行だけを出力するには、sedの出力を抑制する「-n」オプションを使い、「s/置換前/置換後/p」のように指定して、「s」コマンドを「p」フラグ付きで実行します。
コマンド実行例
sed -n s/GNU/gnu/p ファイル名
(「GNU」を「gnu」に置換後、置き換えた行だけを出力する)
cat ファイル名 | sed -n s/GNU/gnu/p
(「GNU」を「gnu」に置換後、置き換えた行だけを出力する)(画面2)
処理を繰り返す
「s」コマンドは、デフォルトでは1行の処理で最初に見つけたパターンを置き換えたら終了します。各行に含まれる全てのパターンを置き換えたい場合は、「s」コマンドに「g」オプションを付けて実行します。
また、「p」フラグと「g」フラグを同時に指定することも可能です。「p」と「g」の指定順はどちらでも構いません。
コマンド実行例
cat ファイル名 | sed s/sed/SED/g
(全ての「sed」を「SED」に置き換える)
cat ファイル名 | sed -n s/sed/SED/pg
(全ての「sed」を「SED」に置換後、置き換えた行だけを出力する)(画面3)
対象とする行を指定する
「s」コマンドが対象とする行を限定したい場合は、「s」コマンドの前に「行番号」または「/パターン/」を指定します(行番号/パターンの指定:本連載第54回を参照)。
コマンド実行例
cat ファイル名 | sed -n 2,5s/GNU/gnu/p
(2〜5行目の「GNU」を「gnu」に置換後、置き換えた行だけを出力する)
cat ファイル名 | sed -n /sed/s/GNU/gnu/p
(「sed」というパターンが含まれる行の「GNU」を「gnu」に置換後、置き換えた行だけを出力する)(画面4)
1文字ずつ対応させて置換する
パターンではなく、1文字ずつ置き換えするには「y」コマンドを使用します。例えば、「y/GNU/gnu/」と指定した場合は「GNU」という単語ではなく、「G」という文字を「g」に、「N」を「n」に、「U」を「u」に置き換えることになります。
「a-z」のような範囲指定はできないので、置き換えたい全ての文字を指定する必要があります。単純に文字を置き換えるだけであれば、「tr」コマンドの方が手軽で便利です(trコマンド:本連載第52回を参照)。
なお、「s」コマンドのようなフラグはなく、行中の全ての文字が置換対象となります。
コマンド実行例
cat ファイル名 | sed y/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/
(大文字を小文字に置換する)
cat ファイル名 | sed y/GNU/gnu/
(「G」を「g」に、「N」を「n」に、「U」を「u」に置換する)(画面5)
筆者紹介
西村 めぐみ(にしむら めぐみ)
PC-9801N/PC-386MからのDOSユーザー。1992年より生産管理のパッケージソフトウェアの開発およびサポート業務を担当。のち退社し、専業ライターとして活動を開始。著書に『図解でわかるLinux』『らぶらぶLinuxシリーズ』『はじめてでもわかるSQLとデータ設計』『シェルの基本テクニック』など。2011年より、地方自治体の在宅就業支援事業にてPC基礎およびMicrosoft Office関連の教材作成およびeラーニング指導を担当。
関連記事
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.