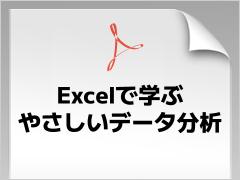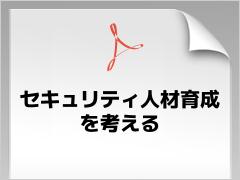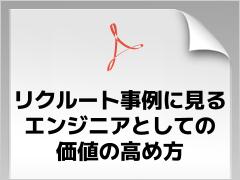繁忙期に打ち合わせを設定するなんて非常識じゃないですか!:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(66)(2/3 ページ)
» 2019年06月03日 05時00分 公開
[ITプロセスコンサルタント 細川義洋,@IT]
債務不履行vs.非協力的態度
ここで、ユーザー企業の業種に注目してほしい。教材販売会社は4月が繁忙期である。
「本業の忙しい中、システムに関する打ち合わせになど出ていられない」というのが本音だ。だからこそ当初スケジュールでは「3月をベンダーの開発期間に充て、同月末にリリースしてもらおう」という考えだった。
「3月の納期が守れず、自分達の都合も考慮してくれずに4月に打ち合わせを入れたスケジュールを提示し、最終的にはそれすら守れず納期が8月まで遅れたのは、ベンダーの債務不履行だ」とするユーザー企業。
それに対し、「4月の打ち合わせを実施しないというユーザー企業の非協力的な態度こそが大幅な遅延につながった」とするベンダー。
少し補足すると、裁判所の判断は「ベンダーが3月の納期を守れなかったこと」については論点としていない。その理由は定かではないが、双方にそれなりに責任があってのことと判断したと推察される。
問題は、ベンダーがユーザー企業と合意のないまま4月以降も作業を続け、にもかかわらず、6月の納期すら守れなかった点だ。
判決の続きを見てみよう。
関連記事
 ユーザーが資料をくれないのは、ベンダーの責任です
ユーザーが資料をくれないのは、ベンダーの責任です
ユーザーが要件定義に必要な資料を提供しなかったため、システム開発が頓挫した。責任を取るべきはユーザー、ベンダー、どちらでしょう? 追加要件を実装しなければ、このシステムは使いません――「旭川医大の惨劇」解説その1
追加要件を実装しなければ、このシステムは使いません――「旭川医大の惨劇」解説その1
ユーザーが要件を次々と追加、変更したために失敗したプロジェクトの責任は、要件追加をやめなかったユーザーにあるのか、それとも、それをコントロールできなかったベンダーにあるのか……。2017年8月に第二審判決が出た「旭川医大vs.NTT東日本 病院情報管理システム導入頓挫事件」のポイントを、細川義洋氏が解説する 恐怖! 暴走社長「仕様は確定していませんが、納品はしてください」
恐怖! 暴走社長「仕様は確定していませんが、納品はしてください」
自社の不手際でプロジェクトが遅延しているのに、ベンダーを訴えたユーザーの社長。勝ち目のない裁判に社長が打って出た理由は何だったのだろうか? ユーザーの「無知」は罪なのか?
ユーザーの「無知」は罪なのか?
不整合データを提供しておきながら、システムが動作しないとベンダーを訴えたユーザー企業。彼らに勝ち目はあるのか?
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.