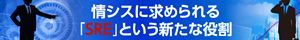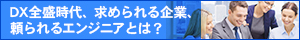|
連載 IT管理者のためのPCエンサイクロペディア 第3回 本家IBM PCの歴史(1)〜IBM PC誕生 元麻布春男 |
|
2回に分けて日本のパーソナル・コンピュータの標準がPC-9801からPC互換機へと移る過程を解説してきた。今回から数回に分けて、本家IBM PCの誕生から互換機の台頭、Intel主導によるPCへの各種新規格の投入といった歴史を紹介していく。
既製品を目指したIBM PCの誕生
日本でメーカーごとに似て非なるアーキテクチャのパーソナル・コンピュータが乱立していたころ、海外、特にパーソナル・コンピュータ発祥の地である米国では、パーソナル・コンピュータのアーキテクチャは実質的に1つに集約されようとしていた。いわずとしれたIBM PCアーキテクチャである。現在使われているPCのソフトウェア互換性のルーツともいえるIBM PCが誕生したのは、1981年8月12日のこと。米国フロリダ州ボカラトンで生まれたIBM PCは、発売後ただちにベストセラーとなり、その後に投入されたIBM PC/XT、IBM PC/ATなどと合わせて、パーソナル・コンピュータの歴史に大きな影響を与えた。
そんなIBM PCだが、ハードウェア的に、あるいはアーキテクチャ的に特筆するようなことはあまりない。搭載されたプロセッサは内部16bit/外部8bitの16bitであるIntel製のi8088(動作クロック4.77MHz)で、割り込みコントローラ(i8259)やDMAコントローラ(i8237)といった周辺チップも、基本的にはCPUメーカーのIntelが用意した標準的なもの(それも8bit時代からある古いもの)が多数を占める。マザーボード上に実装可能なメモリも、初期のIBM PCは標準16Kbytes、最大64Kbytesと、8bitマイコンなみであった(のちに最大256Kbytesまで実装可能なものに切り替えられた)。
 |
| IBM PCの開発時のマザーボード |
| IBM PC誕生20周年記念で公開されたIBM PCの開発時のマザーボード。汎用的な部品を組み合わせることで実現していたことが分かる。 |
ディスプレイ表示機能も、最初から用意されていたのは、モノクロでテキスト表示のみが可能なMDA(Monochrome Display Adapter)と、320×200ドット解像度時に4色、640×200ドット時では1色しか表示できない低解像度のカラー・グラフィックスをサポートしたCGA(Color Graphics Adapter)の2種類のみで、当時のApple Computerや日本メーカーのパーソナル・コンピュータに比べても、見劣りするものであった。強いていえば、IBM PCが標準で容量320Kbytesの5インチ・フロッピー・ドライブ(DOS 1.1の場合)を標準搭載していたことが画期的だったくらいで、スペックを見る限り、当時すでに世界最大のコンピュータ(メインフレーム)・メーカーであったIBMの技術力を感じることは難しい。
このようにIBM PCが、ある意味で極めて凡庸なハードウェアとなった理由については、さまざまなことがいわれているが、最も有力な理由としては開発にかけられる時間が限られていたことが挙げられている。フィリップ・エストリッジ(Philip D. "Don" Estridge)氏(その後に不幸な航空事故により亡くなる)が率いる開発チームに与えられた時間はあまりに短く、Intel製のプロセッサや周辺チップといった「既製品」を使わざるを得なかった、というわけだ。当時の米国は、CP/M*1を搭載したS-100バス*2・マシン上で動作する、WordStarやVisiCalcといったビジネス・アプリケーションを使う人々が現れ始めたころ。パーソナル・コンピュータが、ホビイストだけのものではなくなろうとしていたが、まだ企業でビジネス・ツールとして導入されるには至っていない、という時代である。こうした情勢をうけて、IBMは早急にパーソナル・コンピュータ市場に参入する必要があり、自社技術による開発より、速やかな製品提供を優先した、というわけだ。
| *1 CP/M:Digital Researchが開発したi8080/Z80用OS。8bit CPU時代の代表的なOSの1つで、多くのビジネス・アプリケーションや開発言語が提供された。i8086に対応したCP/M-86もあり、一時はPC-DOS/MS-DOSと市場で競争したが、IBMの標準採用を勝ち取ったPC-DOS/MS-DOSが、サードパーティの支持を勝ち取り、結局は市場を制覇した。 |
| *2 S-100バス:MITS Altair 8800やIMSAI 8080など、1970年代後半に登場した8bit CPU(i8080/Z80)マシンで主に使われていた100ピンのバス。S-100バス・マシンとして、i8080/Z80を搭載したCP/Mマシンの総称的な呼び名にもなっている。 |
筆者は、この開発期間限定説を否定するものではないし、実際IBM PCの開発期間は約1年ともいわれている。だが、ひょっとするとIBMあるいはエストリッジ氏は、あえて「既製品」を選んだのではないか、という気もしている。IBMはPCの発売を前に、MicrosoftやDigital Researchといった、当時の基本ソフトウェア会社に、IBM PC用ソフトウェアの提供を求めている。これも開発期間が不足していたから、という理由付けが可能だが、実際にはソフトウェアの既製品こそが欲しかったのではないか、と思うのである。
 |
| 初代IBM PC |
| 汎用的な部品を採用することで、短い時間で製品開発が行えたという。ただし、その後にPC互換機を生む結果にもつながる。 |
当初IBMは、MicrosoftにROM BASICの開発を、Digital ResearchにPC用OSの開発を依頼したかったのだが、なぜかDigital Researchには断られ、MicrosoftがOSまで手がけるようになった、というのは有名なエピソードだ(IBMにDigital Researchを紹介したのもMicrosoftだといわれる)。このような、当時のパーソナル・コンピュータ界における人気の定番商品を、IBM PC上に揃えることで、プログラマや開発者をIBM PCのサードパーティに引き込みたかった、という狙いがあったとしても不思議ではない。i8088プロセッサを採用した理由の1つとして、すでに蓄積されはじめていたCP/M上の(i8080対応の)アプリケーションの移植を考えて、ということは当然あっただろう。実際、その後にIBM PCは多くのサードパーティを引き寄せることに成功し、それがIBM PC自体の成功にもつながることになった。
IBM PCが実現したオープン・アーキテクチャ
IBM PCに先立つこと約6年、1975年9月にリリースされたIBM 5100 Portable Computer(といっても、5インチCRTディスプレイを内蔵し、重量は20Kgをはるかに超えるものだったが)は、ROMにBASICやAPL(A Programming Language:インタープリッタ言語の一種)、あるいはその両方が搭載された、いわばIBM初のパーソナル・コンピュータだった。ただIBM 5100 Portable Computerは、汎用マイクロプロセッサを用いたものではなく、IBM独自の技術によるものであった。のちのIBM PCと異なり、自社技術によるハードウェアに、自社によるソフトウェアを組み合わせたIBM 5100の価格は最低でも1万ドル近くしたため、一部の研究機関などにしか売れず、商業的には成功していない。エストリッジ氏は、IBM PCをIBM 5100のようにはしたくなかったのではないかと思う(ただし、IBM PCの本体につけられた型番は5150で、アーキテクチャなど、まったく異なるにもかかわらずIBM 5100の系列製品のような扱いになってしまったのだが)。既製品を集めたおかげで、フロッピードライブを内蔵したIBM PCには、IBM製品としては破格の1500ドル前後という安価な値札がつけられた。i8086ではなく、あえて外部8bitバスのi8088を採用したのも、低価格化の実現が念頭にあったからかもしれない。
さて、IBM PCが既製品で構成されていた、ということで避けて通れない話題が「オープン・アーキテクチャ」ということだ。IBM PCの回路図やシステムBIOSのソース・コードが、別売の技術マニュアルで公開されていたのは間違いのない事実である。技術情報が公開されたことで、ソフトウェア、ハードウェアを問わず、サードパーティの参入は容易だったハズだ。しかし、こうした情報が公開されていることと、その2次利用はまた別の話。IBMは、いわゆる互換機市場を立ち上げるために、こうした情報を公開したわけではない。公開されたソース・コードを丸ごとコピーしたBIOSを搭載すれば、当然著作権を侵害することになる。IBMがIBM PCでオープン・アーキテクチャを採用したことは事実だが、互換機やクローンを是認してのものではない、ということは理解しておく必要がある(IBM PCをリリースした時点で、クローンの登場を予見していたかどうかも不明だが)。互換機ビジネスを行うには、IBMとのライセンス契約が必要だったが、そのライセンス料はリーズナブルだった(少なくともPS/2以前は)とされている。既製品を多く採用したPCのアーキテクチャでは、高額なライセンス料など取りようがなかった、ということかもしれない。
もう1つ、オープン・アーキテクチャ関連で触れておきたいのは、IBM PCのマザーボードがいわゆるオンボードI/Oをほとんど持たず、I/Oデバイスを拡張カードとして実装する形式を採用していたことだ。IBM PCのマザーボード上に用意されていたI/O機能は、キーボードとカセットテープ・インターフェイス(カセットテープ・レコーダと接続してカセットテープにデータを記録するためのインターフェイス)くらいで、フロッピーディスク・インターフェイスやパラレル・ポート、ディスプレイ表示機能といったものは、すべて拡張スロットを用いて実装されていた。拡張カードとオープン・アーキテクチャは、直接関係しないようにも思われるが、ディスプレイ表示機能のような基本的なI/Oデバイスまでサードパーティ製品と交換できる、というのは当時の日本製PCでは考えられないことだった。
実際、当時のIBM PCの多くでディスプレイ表示装置(グラフィックス・カード)として使われたのは、純正のMDAやCGAではなく、1982年に発表されたHercules*3のMonochrome Graphics Card(HGC:Herculesグラフィックス・カード)である。Herculesカードは、MDA相当のテキスト表示機能に、MDAがサポートしていないグラフィックス機能を持たせたもので、これに当時としては画期的なグラフ描画機能を持った表計算ソフト、Lotus 1-2-3を組み合わせるのがイケてるビジネス・クライアントだった。
| *3 Hercules(ヘラクレス):1982年設立の老舗グラフィックス・カード・ベンダ。当時は「ハーキュリーズ」と英語読みで呼ばれることが多かった。1999年にフランスの大手マルチメディア機器ベンダのGuillemot(ギルモ)に買収され、現在は同社の1部門となっている。 |
クリーン(質素)な本体に、必要に応じて拡張カードでI/O機能を加える。これもオープン・アーキテクチャという言葉の意味の1つではないかと思うのだが、こうした構造は1つのマイナスを生んだ。それは、必要以上にケースが大きくなりがちであるということだ。IBM PCのみならず、IBM PC/XT、IBM PC/ATと、IBM PCシリーズのケースは、横幅が50cm前後と非常に大きかった。これも、5〜8本用意された拡張スロットに大型の拡張カードを実装することを想定していたからだ。ケースが鉄製であることも含め、IBM PCシリーズには古き良きアメ車的な雰囲気が漂う。
| INDEX | ||
| 第3回 本家IBM PCの歴史(1)〜IBM PC誕生 | ||
| 1.オープン・アーキテクチャのIBM PC誕生 | ||
| 2.IBM PCからIBM PC/XT、PC/ATへの進化 | ||
| 「System Insiderの連載」 |
- Intelと互換プロセッサとの戦いの歴史を振り返る (2017/6/28)
Intelのx86が誕生して約40年たつという。x86プロセッサは、互換プロセッサとの戦いでもあった。その歴史を簡単に振り返ってみよう - 第204回 人工知能がFPGAに恋する理由 (2017/5/25)
最近、人工知能(AI)のアクセラレータとしてFPGAを活用する動きがある。なぜCPUやGPUに加えて、FPGAが人工知能に活用されるのだろうか。その理由は? - IoT実用化への号砲は鳴った (2017/4/27)
スタートの号砲が鳴ったようだ。多くのベンダーからIoTを使った実証実験の発表が相次いでいる。あと半年もすれば、実用化へのゴールも見えてくるのだろうか? - スパコンの新しい潮流は人工知能にあり? (2017/3/29)
スパコン関連の発表が続いている。多くが「人工知能」をターゲットにしているようだ。人工知能向けのスパコンとはどのようなものなのか、最近の発表から見ていこう
|
|