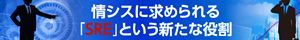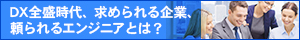|
連載 IT管理者のためのPCエンサイクロペディア 第4回 本家IBM PCの歴史(2)〜IBM PCからPC互換機へ 元麻布春男 |
|
前回の「第3回 本家IBM PCの歴史(1)〜IBM PC誕生」では、IBM PCの誕生とその歴史について話をした。ここでIBM PCは、汎用的な部品を採用し、「オープン・アーキテクチャ」を実現していたことを説明した。実は、IBM PCがオープン・アーキテクチャであったことが、そのあとのIBM PC、ひいてはPC業界全体を左右する大きな流れを作った。今回は、そのあとのIBM PCと、IBM PCと互換性を持ったPC互換機の誕生について話をしよう。
PC互換機の登場
IBMがリリースしたPCシリーズのパーソナル・コンピュータは、瞬く間に米国市場を席巻した。特に、それまでパーソナル・コンピュータが浸透できないでいた大企業で圧倒的に支持された。これは、やはりIBMのブランド力のおかげだろう。初期には米国にもDECのRainbowなど、日本のPC-9801と同様、IBM PC非互換のMS-DOSマシンも存在したが、これらが永らえることはできなかった。
もはやIBMの成功はだれの目にも確かに思えたが、そこにはすでに大成功を脅かす影が迫りつつあった。それは互換機の登場である。IBM PCシリーズの成功は、IBMのブランド力とオープン・アーキテクチャが両輪となって築いたものだが、オープン・アーキテクチャは同時に互換機の登場を容易にする。もちろん、公開されたBIOSのソース・コードをそのまま利用するなどといったことは許されるハズもないが、すべての仕様が明らかな以上、それと同等の機能を持つものを、別の方法で実現することは困難ではなかった。互換機の登場は、オープン・アーキテクチャ路線を採用したIBM PCシリーズにとって、成功と表裏一体のものだったかもしれない。実際、PC互換機の歴史は古く、IBM PCがリリースされた約半年後の1982年2月には、Compaqが設立されており、翌1983年にはCompaq初のPC互換機「Compaq Portable PC」が発売されている。
だが、IBMにとって本当に頭を悩ませたのは、もう1種類の互換機かもしれない。それはいわゆる「クローン」だ。Compaqなどのいわゆる大手PCベンダがリリースしたPC互換機が、IBMが発売するPCシリーズと機能的に互換性を持つだけであるのに対し、クローンは機能的な互換性だけでなく、IBM PCシリーズを構成するコンポーネント・レベルでの1対1の互換性をうたう。つまり、クローンのマザーボードは、IBM純正のマザーボードと大きさ、形状、取り付け穴の位置(これらを総称して「フォームファクタ」と呼ぶ)まで完全に同じ。ケースや電源ユニットにも同じことが当てはまる。
確かにPCのアーキテクチャは、既製品を多用したものであり、独自性に乏しい。それでも、ケースを含めた各コンポーネントのデザインなどには、IBMによる設計や開発といった要素が含まれている。IBMにとってクローンは、こうした部分にタダ乗りするようなものだ。しかも、クローン機を販売するベンダの多くは規模が小さく、そこからライセンス料を徴収するのも容易ではない。一方、Compaqに代表される大手PCベンダは、独自のエンジニアリングを行うため、特許のクロスライセンスといったことも行いやすい。
しかし、最終的に市場はクローンを支持した。IBM PC/ATと同じフォームファクタの電源、ケース、マザーボードなどが、主に台湾のベンダから潤沢に供給され、デファクトスタンダードとなったのである。こうしたクローンは、この時点では大手PCベンダが開発したPCほどの最先端の機能を備えたものではなかったが、「何もかもがIBM製のPCと同じ」という安心感からか、通信販売や地元の小規模PCショップを中心として着実に浸透していったのだ。
リーダーの座から脱落したIBM
 |
| Intel386 DX |
| x86アーキテクチャを採用したIntel初の32bitプロセッサ。1.5μmプロセスで製造され、27万5000トランジスタが実装されていた。なおIntel386までは、浮動小数点演算ユニットは統合されておらず、科学技術計算などを高速で実行するためには外付けの数値演算プロセッサ「i80387」が必要とされた。 |
1980年代半ばになって、互換機やクローン以外にIBMを悩ませることになったのが、プラットフォームの定義者としてのリーダーシップの問題だ。この当時販売されていたPCは、みんなIBM PC互換、あるいはIBM PC/AT互換のものばかりという状態になった。そして、そのプラットフォームを定義したのは、IBM PCやPC/XT、PC/ATをリリースしたIBMである。つまり、IBMこそがPCプラットフォームのリーダーであり、IBMだけがその方向性を導く能力を持つと信じられてきた。
ところが、それを揺るがすような事件が起きた。Intelが1985年10月に発表した新しいプロセッサ「i80386*1」を、IBMより先にCompaqやALR(Advanced Logic Research、のちにGatewayに買収される)といったサードパーティが採用したのである。Intel初のx86アーキテクチャ採用の32bitプロセッサであるi80386は、32bit化によるアドレス空間の拡大や、仮想86モードのサポートといった機能的な改善に加え、動作クロックが16MHzに高速化された(1989年に33MHzまで高速化される)。このi80386をどうやって16bitアーキテクチャのIBM PC/ATに取り込むかというのは、なかなか難しい問題であった。
| *1 そのあと、i80386は「Intel386 DX」と呼ばれることになる。また、外部バス幅を16bitにした「Intel386 SX」も廉価版として1988年に出荷されている。 |
 |
| CompaqのDeskpro 386 |
| Flexアーキテクチャを採用し、ISAバスを分離したのが特徴。IBM PC/ATまでは、ISAバスはプロセッサ・バスの延長としていたことから、プロセッサの動作クロックが上がると、必然的にISAバスのクロックも上がってしまい、互換性が維持できないという問題が生じた。この問題をプロセッサ・バスとISAバスを分離することで解決したのが、Flexアーキテクチャである。 |
i80386搭載のIBM PC/AT互換機を実現するためにCompaqが採用したFlexアーキテクチャは、外部バス(ISAバスまたはATバスとも呼ばれる)をプロセッサ・バスとメモリ・バスから完全に分離するものだった。つまり、メモリのように高速性が要求されるものは、プロセッサの外部バスに直接接続されたメモリ・コントローラに接続し、そのほかの周辺機器類はチップセットが提供するi80286ベースのIBM PC/ATと互換性を持つ16bitバスを利用するようにした。この方法では、周辺機器(拡張カード類)は32bitアーキテクチャの恩恵を受けることができないが、当時の周辺機器でISAバスの帯域幅を上回るほど高速なものはそれほど多くなかったため、実害は顕著ではなかった。唯一、ISAバス上のバスマスタからのメモリ・アクセスという問題が生じた。ISAバスにある24bitアドレス空間上のデバイスは、そのままでは32bitアドレス空間上の任意のアドレスにアクセスできないからだ。ただ、これもいったん24bitアドレス空間内にバッファし、プロセッサで本来のアドレスに転送し直す、ダブル・バッファリングというソフトウェア的な解決が可能だったため、大きな障害にはならなかった。
このプロセッサ・バスとISAバスを完全分離したアーキテクチャは、既存のPCとの互換性を維持したままで、より高速なプロセッサの採用を可能にしたため、ほかのPCベンダもこぞって採用した。ここに、現在のPCの基礎となる、メモリ・バスの外部バスからの分離が確立したことになる。問題は、「こうしたエンジニアリングを行ったのが、IBMではなかった」ということだ。Compaqのi80386マシンであるDeskpro 386が1986年に登場したのに対し、IBM製のi80386マシンであるIBM PS/2は、1987年まで待たなければならなかった。少なくとも1年の間、PCアーキテクチャのリーダーシップの点で、IBMは遅れをとってしまったのである。
Intel対互換プロセッサ・ベンダ
ところで、Compaqが開発したFlexアーキテクチャの恩恵は、何もi80386以降のプロセッサのみが享受したわけではない。Intelがi80386をリリースした当時、i80286 CPUはIntelの正式なライセンスにより、Intel以外のAMDやHarris Semiconductorといったメーカーからセカンドソース供給が行われていた(ほかにもSiemensや日本電気がIntel製CPUのセカンドソース製造を行っていたことがある)。問題になったのは、Intelとこうしたセカンドソース会社の間のライセンス契約がi80386や数値演算コプロセッサの製造権を含むものかどうかという点で、この問題は長期にわたる裁判で争われることになった。もちろん、AMDやHarris Semiconductorは、i80386の製造権を主張したわけだが、裁判になったことで、顧客がIntelの法的対抗措置を恐れ、作っても売れるかどうか疑わしい状態となってしまった。
そこで、AMDやHarris Semiconductorは、独自にi80286の高速化を行った。Intel純正のi80286が動作クロック12.5MHzどまりであったのに対し、AMDやHarris Semiconductorは16MHzや20MHz、さらには25MHzといった高速な80286を製造した。こうした高速な80286 CPU搭載マシンでも、メモリ・バスとISAバスを分離するというアイデアが生かされた。高速な80286 CPUを搭載したマシンは、リアル・モードのアプリケーションに限定すれば、同じクロックのi80386マシンよりわずかに高速で、一部で好評を博したが、i80386の仮想86モードを利用したメモリ・マネージャ(前回紹介したQEMMなどがこれに該当する)や、それを生かしたマルチタスク環境(QEMMの開発元であるQuarterdeckのDESQviewなど)の登場により、徐々に分が悪くなっていった。これを決定的にするのがWindows 2.11〜Windows 3.0の登場と普及である。なお、現在はIntel以外のプロセッサをかたくなに採用しないDell Computerだが、この当時はAMDやHarris Semiconductorの高速な80286を搭載したシステムの販売を行っていた。
| 更新履歴 | |
|
| INDEX | ||
| 第4回 本家IBM PCの歴史(2)〜IBM PCからPC互換機へ | ||
| 1.互換機PCベンダの誕生 | ||
| 2.MCAの失敗とEISAの登場 | ||
| 「System Insiderの連載」 |
- Intelと互換プロセッサとの戦いの歴史を振り返る (2017/6/28)
Intelのx86が誕生して約40年たつという。x86プロセッサは、互換プロセッサとの戦いでもあった。その歴史を簡単に振り返ってみよう - 第204回 人工知能がFPGAに恋する理由 (2017/5/25)
最近、人工知能(AI)のアクセラレータとしてFPGAを活用する動きがある。なぜCPUやGPUに加えて、FPGAが人工知能に活用されるのだろうか。その理由は? - IoT実用化への号砲は鳴った (2017/4/27)
スタートの号砲が鳴ったようだ。多くのベンダーからIoTを使った実証実験の発表が相次いでいる。あと半年もすれば、実用化へのゴールも見えてくるのだろうか? - スパコンの新しい潮流は人工知能にあり? (2017/3/29)
スパコン関連の発表が続いている。多くが「人工知能」をターゲットにしているようだ。人工知能向けのスパコンとはどのようなものなのか、最近の発表から見ていこう
|
|