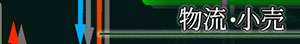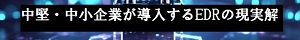情報システム部門、成功と失敗の法則:BizCompスペシャル(2/2 ページ)
■Part.2
先進“情シス”の成功法則
Part1では「IT部門の典型的な課題」を見てきた。では、IT活用先進企業ではこれらの問題に、どのように取り組んでいるのだろうか? アットマーク・アイティ編集局ではIT先進企業の情報システム部門担当者に話を聞いた。
清水建設・情報システム部課長の安井昌男氏は、情報システム部門の存在意義について次のように語る。
「IT投資にかかわる意思決定と、その評価および実施を担うこと」
しかし、こうした存在意義を意識して機能している情報システム部門の数は少ない。安井氏は「国内に300万人いるといわれている企業情報システム従事者のうち、キーマンとして活躍している人は数パーセント未満ではないか」と見ている。何が問題なのだろうか。
人材はやはり難題
前提としての“ビジネススキル”
人材に関する課題はすべてにかかわってくる。ダイヤモンドリース・情報システム部長の保田徳太郎氏は「社内IT化の課題は、ほとんどが“人”の問題に行き着く」と打ち明ける。
何より求められるのが、ビジネスとITの双方に関する一定以上のスキルだ。“素養”と表現した情報マネージャもいる。例えば、利用者部門に対する「提案力/企画力」の有無。提案に際し、必須となる「業務知識」への造詣。またエンドユーザーからの要求を正しく理解し、プログラム開発部隊やITベンダに的確に伝達できる「コミュニケーション力」や「プレゼンテーション力」も重要だ。
「自社のビジネスモデルに関する基本的な知識と、それを支える業務知識。後はコミュニケーション力や企画力など、基本的なビジネススキルがあれば、極端な話、詳細なIT知識は必要ない」と断言する情報システム部長もいる。
しかしながら、実際には「IT」だからと、“パソコンおたく”のような人材が多く集まってしまうことも多く、また社内的にも情報システム部門は「IT担当」と見られるため、そもそもの思考がIT中心になりがちだ。
またIT業界ならぬ一般企業では、ITに興味を持つ人材が集まらなかったり、本業から外れたと見られるIT部門への配属を不満に思い、早々に退社する社員もいる。また、ITへの適応が優れている人材は、「せっかく育てても流出してしまう」と嘆く声も聞かれる。
技術を見抜く目の必要性
その一方、技術知識を重視するのが前出の安井氏だ。「情報システム部門の興味関心事にムラがあってはならない。こうしたビジネススキルに加え、社内のIT専門家として必要な技術知識の習得を忘れてはならない」と訴える。技術が分かっていなければ、課題を解決する適切なITを選択できないからだ。それに知識の欠如は、経営層や利用者部門に対するプレゼンテーションにも影響する。「この業務課題解決のためにごのITが必要なのか、一連のストーリーとしてきちんと理解していなければ、他人に対して説明することもできない」。見極める力があってこそ、ビジネススキルも生かされるわけだ。
このように「ITだけでなく、業務知識と基本的なビジネススキルを併せ持ったバランスの良い人材」は理想的だが、実際にそのような人材を採用・育成するのは非常に難しい。
人材育成と採用に工夫を
その点でIT先進企業での取り組みは、参考になる点が多い。例えば清水建設では、課題発見・開発・展開・運用を最短で実施できるよう、チーム力を重視。「個人を育成するというより、チームの能力を高めると考えることが重要」(安井氏)という。まず、業務への理解を深めるためにOJTを実施。実際の作業現場に出て自社業務を体で覚え込むわけだ。建設業最大手である同社の建設現場は、プロジェクトマネジメント力を付ける実践の場でもある。そしてビジネス課題から具体的なITに落とし込むノウハウとしてモデリング技術を中核に据え、課題発見からIT開発へと一気通貫で実行するため、習得と普及を推進している。
ダイヤモンドリースでは、新人ITスタッフに対し、まず初めに「運用」を経験することを義務付けている。保田氏によると、「社内システムの全体像を把握するため」だという。全社システムのアーキテクチャを実地に体験することで、バランスを崩さず最適なITを企画立案できるようになる。オープン環境下のシステムを動かすITスタッフには欠かせない知識だ。これにより、全体最適の観点で業務プロセスを改善できるというメリットもある。
コクヨ本社内の情報戦略部長を務め、今年4月に設立されたコクヨビジネスサービス代表取締役副社長の小嶋浩毅氏は「本当に技術だけを極めたいのなら、SI企業に転職すべき」としながらも、「多くの企業が、IT部門にふさわしいキャリアパスプランを確立できていないのは事実」と語る。そこで同氏が提案する1つの解は「IT部門を社外に切り離す」というものだ。独立させることで、「IT技術職」と「IT企画職」というIT部門独自のキャリアパスを用意し、個人の能力や資質、希望に応じて選択できるようにするのも一策だ。
ユーザー課題を発見し、企画を推進する
ユーザー部門との関係を再構築
次に求められるのがユーザーの課題を発見し、IT企画の企画・立案力を行う能力だ。これを効果的に実践するには、どうすればよいのか。先進企業の取り組みから見ると、「ユーザーとの距離を縮める」という方策が考えられる。
横浜に本社を置く三技協では、社内改革を担う「デジタルビジネスセンター(DBC)」と、ITの企画・開発・検討を担当する「IT-Engine」の2つの部門が協力し合い、業務改革とITを融合させる施策を取っている。DBCで企画立案したシステムを、技術的な観点から検証し、実際の開発プロジェクトを指揮するのがIT-Engineという役割だ。さらに同社では、社内業務部門から20代後半〜30代前半の若手を選抜し、「情報エキスパート」育成のためのトレーニングを週1回実施。ここでいう情報エキスパートとは、「業務課題を発見し、改善案を考え、適切なITを企画できる人材」のこと。IT-Engine部長の中村善則氏は「ベテラン社員がこの役を担うとなると、長年の人間関係や上下関係に挟まれて現場で自由に動きにくい。むしろ現場や会社に染まり切っておらず、社内のしがらみも少ない若手の方が伸びを期待できる」と説明する。こうした情報エキスパートを業務部門に置くことで、エンドユーザーとの距離を縮める工夫も見られる。
ダイヤモンドリースのIT推進は、システムの開発と運用を行う情報システム部だけで行うのではなく、「ユーザーインターフェイス・グループ」と呼ばれるユーザー部門の代表者を交えて行う形になっている。また同社では、経営層を始め全社員にシステム部門/ITを理解してもらうため、2〜3カ月に1度「システム委員会」を実施。経営層に基幹システムの運行状況や開発プロジェクトの進ちょくを報告し、新規システム施策へのリクエストをヒアリングするなど、部門やシステムへの関心を高めてもうらうよう工夫を凝らしている。
ユーザー教育は「着実に」「分かりやすく」
とはいえ、エンドユーザー全員がITを使いこなせるかというと、そういう会社ばかりではない。特にサービス業や小売業など、コア業務にITがあまり必要ない場合、社員のITリテラシーが低いという問題がある。そのため、システム部門に対する提案がまったく発生しないというケースも発生する。経営者側からすると、「ITを使ってビジネスの効率化を進めたい」が、情報システム部門もエンドユーザーもどうしていいのか分からない、といった例だ。
こうした場合は、より積極的な情報システム部門が求められる。ある小売業の情報システム部長は、「ITを使えば、こんなに業務が楽になる・戦略が立てやすくなるなど、効果が見えるシステムを提案することが重要。一気に社内システムを改善するのではなく、一歩一歩効果を実感できるITを企画できるかがポイントだ」と語る。
IT調達力の強化ポイント
コスト削減要求にも“説得”と“信頼感”を
そして最後に、忘れてならないのがコストの問題だ。ある情報システム部長は「いくらITへの理解があっても、スポンサーである経営者から見ると、開発・運用コストは高く見える。10円でも安く抑えたいのが本音」と語る。
そこでモノをいうのが、プレゼンテーション力だ。経営者やエンドユーザー部門に対し、「なぜこのITが、いま必要なのか」「これを導入したら、どのような効果が期待できるのか」などをきちんと説明できなければ、必要コストとして認めてはもらえない。ダイヤモンドリースの保田氏も同様に、経営陣にIT導入の理由や必然性をきちんと語り、信頼感を得るためのコミュニケーションとプレゼンテーションの能力は「絶対条件だ」と語る。つまり、コスト問題の解決についても、ITスタッフのスキルにかかっているといえる。
やはり背景には技術力
とはいえ、事前の情報収集力も非常に重要なポイントだ。コクヨビジネスサービスの小嶋氏は「コストについての疑問がきちんと解けない限り、導入に踏み切ることはまずない」と断言する。例えば、メインフレームからオープンシステムへの乗り換えや、オープンソースの採用についても、開発にコストや工数が掛かったり、システム構成が複雑になったり、バージョンアップ費用や不具合への対処などのランニングコストなどをすべて明らかにし、比較検討しないことには「提案もできない状態」だという。
ここで気を付けなければならないのは、ITベンダのいうことをうのみにしないことだ。「有効な手段は、実際にその取り組みに着手している企業の情報システム部門に話を聞き、実際の評価や掛かった総費用を聞くこと。こちらも気付かなかったメリットやデメリットを教えてもらうことで、コストの妥当性についてより客観的な判断が下せる」(同)。
もちろん技術力がある情報システム部門なら、社内での開発・運用を前提にLinuxなどの新しい技術を積極的に採用することも可能だ。実際、コスト削減に向け、オープンソースのOSやデータベース、開発環境などの技術検証にいそしんでいる情報システム部門もいる。
清水建設の安井氏も「コスト削減のプレッシャーは、大きなものがある。われわれの取り組みとしては、まず開発プロセスとプロジェクトマネジメント力を確立させること。そして、実体が分かりにくいソフトウェアの開発について、各プロセスのポイントで成果物を定義するなど可視化させることで、適正な開発コストを割り出す工夫をしている」と語る。
インタビューの結果、業種や規模、IT化への取り組みの進み具合を問わず、どんな情報システム部門も共通する課題・悩みを抱えていることが分かった。そして先進企業に共通するのは、こうした課題を解決するため、社内に情報システム部門の活動を“見せる”ように働き掛けていることだ。そしてこうしたノウハウや課題を、あらゆる情報システム部門が共有できるような仕組み作りが、いま最も望まれていることなのである。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
人気記事ランキング
- 生成AIで素人が“ちゃんと動くソフトウェア”を作れるのか
- 「Fortinet FortiSIEM」にCVSS v3.1スコア10の脆弱性 初期パッチで修正漏れ ただちに確認を
- 高性能な特化型生成AIを安く作る方法が登場 「進化的モデルマージ」の基礎論文を読む
- ルーターは“消耗品”と心得よ 脅威から身を守るための製品選定のコツ
- WAFの限界はどこにある? Assetnoteが「WAF回避」による攻撃テクニックを紹介
- コカ・コーラはなぜ生成AI導入を急ぐのか? Microsoftとの提携拡大に1700億円投資の理由
- Microsoft、VBScriptの段階的な廃止のスケジュールを公開
- 「AIに魅了され過ぎは危険」 サプライチェーンの専門家が注意を促すワケ
- リソースが足りない企業がやるべき、“最低限で効果的なセキュリティ対策”を考えよう
- 「最高レベルセキュリティ備える」はずのMITREはなぜ侵入されたか? 調査結果が発表