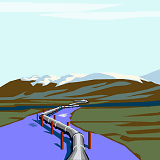企業の中を情報が流れる“3つの川”を考慮せよ:企業システム戦略の基礎知識(16)(1/2 ページ)
企業そのものを情報処理システムと見立てたとき、今日の企業には3つの情報の流れ──別々の川が流れている。「企業三川」モデルで、現代の企業システムを整理してみよう。
企業の中をさまざまな多くの情報が日々、流れている。そして、その流れは必ずしも1つだけではない。少なくとも「枯渇した川=業務標準」「汚れた大河=基幹業務システム」「地下水路=パソコン・ネットワーク」という3つの主な川がある。企業システム戦略を考えるうえで、少なくとも、この3つの川の存在を常に頭に入れておく必要がある。さもないと、きれいな水(情報)を清々と流すことができない。この水を企業体を流れる血液だと見なすこともできる。血液が汚れたり、滞留したりしていては、健康な体を維持することはできない。
枯渇した川──業務標準
会社の業務標準というのは、情報の流し方を規定したものだ。誰が、誰に、なぜ、何を、いつ、どのようにという5W1Hを、それぞれの業務について明文化してある。そして、これは会社という情報処理システムの基本設計図でもある。コンピュータがなかった時代は、この流れが唯一無二のものであった。少なくとも公式には。
しかし、残念なことに多くの会社では、この基本設計図は最初から全体最適を意図して設計されたものではない。少しずつ、仕事が増え、人が増え、組織が増えてくるに従って、それこそ個別最適、ツギハギ的に増殖してきたものなのだ。そのため、実際の現場では、この流れに乗らない業務や情報が、至るところに存在している。
また、紙に書かれた業務処理の流れをすべての関係者に周知するのが難しかった。いったん人々の頭の中に入った業務処理の流れは、時間の経過とともに少しずつ異なる解釈が加えられ、そして、その少しずつ異なる業務処理の流れが口伝によって新入社員に伝えられていった。これは、業務というものが環境や状況に合わせて変化していくものである以上、当然の成り行きだ。しかし、そうして変化していく業務を、適時、業務標準に反映して、社内に周知するのは至難の業だ。
さらに業務標準から少しくらい外れていたところで実害がなければ、それを厳しくとがめる必要もない。また、業務標準は、あくまで標準であり、プラスαの業務処理を完全に否定するものではなく、個人の創意工夫が活かされる余地が残されている方が良い(ISO 9000では、品質保証という面から厳しくチェックされ、標準の改訂と実際の業務の整合性が保証されなければならないとされるが)。
そして、このような状況の中で大型コンピュータが導入されて、基幹業務システムというものが構築された。これは、明らかに新しい情報が流れる大河だ。そして、当初は、この基幹業務システムと業務標準は同じものである“はず”だった。ところが、この川を設計した人たちは、これまた始めから全体を意識して設計をしなかったのだ。
現場での現状の仕事のやり方を、そのままコンピュータの上に再現してしまったのである。この段階で、業務標準と基幹業務システムという2つの異なる川ができてしまったのだ。さらに不幸なことに、紙の業務標準よりもコンピュータ上に存在する基幹業務システムの方が正しい流れだと皆が思い込んでしまった。そのため、誰も業務標準という川の流れに沿って、情報を流さなくなってしまった。ただの紙でしかない業務標準は、こうして生きた情報が流れない「枯渇した川」となっていったのである。
汚れた大河──基幹業務システム
そして、長年の間に基幹業務システムは、その時代ごとに業務担当者の思惑で、さまざまに手が加えられた。業務標準を改定するのは大変なことで、所定の手続きにのっとり、トップの承認が必要であった。ところがなぜか、基幹業務システムは各業務部門の担当者がシステム部門に変更依頼書を出すだけでよかったのだ。そしてシステム部門は、業務担当者の依頼には抵抗ができなかった。たとえ抗弁を試みても、業務部門を助けるのがシステム部門の役目だといわれると、引き下がらずを得なかった。
かくて基幹業務システムと業務標準は、さらに別々の川の流れとなっていったのである。困ったことに、業務がコンピュータ化された組織では、紙の業務標準よりも基幹業務システムの流れが優先された。公的には業務標準が正なのだが、実務的には基幹業務システムが正なのである。
加えて困ったことにトップは業務標準は知っているが、基幹業務システムの実態は知らないという状態になった。トップはシステム計画稟議書に最終的なハンコは押したが、基幹業務システムの基本設計書をレビューして承認していないし、読んだこともない。つまり、現場で行われている業務とトップが認識している業務にギャップが生まれ、これが現場とトップの乖離(かいり)を生んでしまった。コンピュータ化したことで、会社の業務実態がブラックボックス化してしまったのだ。
それでも、すべての業務処理が基幹業務システムの上で行われていれば良かったかもしれないが、末端の細かな業務処理までをすべて取り込めるほど基幹業務システムは融通が利かなかった。やはり、現場では、基幹業務システムから出てきたアウトプットを紙の伝票に転記するなどの作業が皆無にはならなかったため、業務効率化はいま一歩であった。
そのため、基幹業務システムに多額の投資をする計画稟議書にハンコを押したのに、一向に計画に示されている業務効率化によるコスト低減、利益率向上など経営上の効果が見えてこなかった。とうとう、トップはコンピュータや基幹業務システムに「金食い虫で役立たず」というレッテルを貼ってしまったのである。こうして、基幹業務システムは、スパゲッティのように絡み合った、そして情報がよどんだ「汚れた大河」となっていった。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
人気記事ランキング
- 江崎グリコ、基幹システムの切り替え失敗によって出荷や業務が一時停止
- 生成AIは2025年には“オワコン”か? 投資の先細りを後押しする「ある問題」
- Microsoft DefenderとKaspersky EDRに“完全解決困難”な脆弱性 マルウェア検出機能を悪用
- 「Copilot for Securityを使ってみた」 セキュリティ担当者が感じた4つのメリットと課題
- 「欧州 AI法」がついに成立 罰金「50億円超」を回避するためのポイントは?
- 日本企業は従業員を“信頼しすぎ”? 情報漏えいのリスクと現状をProofpointが調査
- 「プロセスマイニング」が社内システムのポテンシャルを引き出す理由
- AWSリソースを保護するための5つのベストプラクティス CrowdStrikeが指南
- VMwareが「ESXi無償版」の提供を終了 移行先の有力候補は?
- トレンドマイクロが推奨する、長期休暇前にすべきセキュリティ対策